前の頁へ戻る この自叙伝のトップへ戻る
ご意見ご感想ご提案 email
![]()
花街女性 の出自
ところで、以前から考えているのだがどうも解らぬことがある。 それは、芸者になる女性たちの一般的な出身はどういう家庭であったろうということである。
叔母、しほ の生家、つまり私の母の実家はもちろん金持ちではなかったが、貧乏でもなかった。 村の内ではどちらかと言えば所有する田圃が多い方であった。 いわゆる作男(サクオトコ)すら居たと謂う。 であればこそ、祖父が後妻の子供たち数人を連れて新宅隠居し、一軒の家が二軒になっても、なお両家がそれぞれ一人前の百姓であり得たのである。 そう考えると、貧乏でやむを得ず娘を養女にやったと謂うわけでもなさそうだ。
しかし叔母が養女に行った先は姫路の髪結いであったのだから、後日芸者にでもするつもりであったろうことは多分に推測出来たのではないか。と、すれば芸者になること自体あまり忌避すべき事柄とは思わぬ社会通念が存在していたと考えられる。
むかし子沢山の場合、一人や二人の子供を他人に呉れてやるということなどあまり気にしなかったのではないか。かっての松竹の<母もの映画のように、わが子をしっかと抱きしめて、「お母さんが生きている限りおまえを他所へやったりなど決してしないからーー」、というようなウェットな社会感覚は少なかったのではないかと考えられる。
私がそう考えるに至ったのは、もう一つ似たような例を身近に知っているからである。 それは、私の家内の叔母も同じような環境のもとで、やはり芸者に出ていたという事実があるからだ。家内の母の実家も山奥でどちらかといえば裕福な農家であった。 事実、兄弟で社長という肩書を持った人もいるし、総領は夫婦とも学校の先生をしていて、いはば村の有力者である。 だが、そのうちの一人の姉妹はまぎれもなく芸者であった。 この芸者をしていた家内の叔母に当たる人は、後に土地の有力者だった旦那の嫁になって、旅館や質屋を経営していた。旦那が亡くなった折の葬式には、府知事を始め多くから寄せられた花輪が町内を埋めたというから、いろいろな公職を勤めていたのであろう。 この人も、食えぬから芸者になったとは考え難い。
別の見方をすれば、芸者になるというのは田舎でも少々ましな農家の娘たちであったと考えられぬこともない。 なぜなら、いよいよどうにもならぬ水呑百姓の娘では、例え素朴な躾(しつけ)にしろそれが出来ていようとは思えぬし、概して言えば容貌もあまり良くないので、磨きのかけようもないと云う事実を、田舎生まれの私は知っている。 いくら都会の花柳界で磨きを受けるにしても、天性が利発でなければ芸者として成功するとは思い難いし、そしてそのような娘は多くの場合少々ましな農家の出身であると考えるのが妥当な処だろう。
すこし方角は違うが似たような誤解を解くべき話がある。
昔、私がハワイにいた頃(昭和32年)、日系一世の老人たちがよく次のようなことを言っていた。
日本ではアメリカ移民に行った人々は貧乏で食えなかった農家の子弟たちであると誤解しているようだが、事実は違っていて、むしろ少なくとも村会議員程度の裕福な農家の出が殆どであった。 そうでなければ、高い船賃や当座の生活費などを支出できる筈がないではないか、と言うのである。しからば何故、移民が貧乏な出であると誤解されたのかと言えば、苦力(くーりー)としていわゆるデッキパッセンジャーで渡米した中国人と、些かの金を持っていた日本の官約移民がごちゃ混ぜにされ同一視されたからだそうである。
芸者の場合でも人々が先ず考えるのは、貧乏ゆえに人身売買の対照にされた不幸な女たちと云う労農文学的パターンである。 これは改めるべき偏狭な図式ではなかろうか。早い話が俳句の大先生、山口誓子の姉さんは確か赤坂か柳橋きっての名妓である。そして彼、山口誓子は東大出の学者である。 姉さんが貧乏で、やむを得ず芸者になったとは思えない。
次に考えてみるべきは、芸者の身請け、または落籍と謂うことである。
旦那が金を払って馴染みの芸者を身請けし、後は自分の自由な所有物にする人身売買に近い行為という定義はどうやら誤りのようだ。 むしろ、芸者という職業を持つ女性たちの職業上の普遍的な通過儀礼が落籍という手続ではなかったろうか。その通過儀礼の折、もし旦那が一人身であれば女性の方は奥様と呼ばれる、もし先に女房が存在すれば二号さんということになる。
明治の元勲桂太郎の奥さんはもと幾松という芸者であり、戦後駐米大使をした武内竜次の奥さんも赤坂の芸者であったことは有名な事実である。 反対に、三島由起夫の「宴のあと」でプライバシー訴訟にまで発展した般若苑のお内儀などは後者の例である。
かって大平内閣の頃、私は経済界主幹の佐藤正忠氏に伴われて渋谷道玄坂の或る料亭へ数回行ったことがある。 そこの女将は大平首相の二号さんとして有名で、そのため料亭は政財界人で日夜おすなおすなの大繁盛であった。 私もお目に掛かったことがあるが、あまり美人だとは思えなかった。
佐藤氏がこういう話を聞かせてくれた。 女将は芸者をしていた若い頃から大平氏と特別の間柄であった。 大平氏が初めて選挙に打って出たとき、親分の池田勇人が、女性問題は選挙の票に響くので女性との縁を切るよう勧めた。
大平氏は、折角長年頼りにしてくれて割ない仲になっている女性を泣かせてまで選挙に出るような薄情な真似は男としてできぬ。 もし、どうしても分かれろと言うのであれば、選挙に出るのを諦める、と見栄を切ったという。 そこまで言われては、いくら親分の池田勇人もそれ以上強要できず終いであった。
ところが大平氏は、二回目の選挙のとき軍資金が足りなくて、あわや落選という瀬戸際に立った。その折、彼女は道玄坂の料亭を担保に入れて銀行から金を借り、それを大平氏に貢いだ。 おかげで大平氏は再当選できたと謂う。これが美談となり、そして常に似たような立場にたつ可能性のある政治家たちの心情を揺すぶって、女将の料亭は今日のような繁盛をみるに至ったと謂うのである。
以上のような例は余程特殊と考えられそうだが、実際にはよくあることと思える。 なぜなら、芸者を落籍する旦那というのはたいてい実業家であろうし、実業家が事業でピンチに陥る例は枚挙にいとまがない。 そうした場合、心を通わせた女が旦那に貢ぎ込むのは当然の成行きである。
つまり、旦那と落籍された芸者の間柄は、アメリカ南部の農場主と買われた奴隷、というような南北戦争当時の物語ではなく、女性の側がたとえ奥様と呼ばれようと、また世に謂う二号さんの立場であろうと、何れにしろ心を通わせた対等の男女であったと考えるべきである。
また、西洋の諺に、「侯爵夫人と高級娼婦の差は年金があるか無いかの違いだけ」というのがあるが、仮に落籍されていない芸者の場合でも、もし彼女が花柳界の一流であれば、彼女に対する社会の評価も、そして彼女の交友関係も一流であったと考えられる。オペラ「椿姫」の舞台でヴィオレッタが話をする相手は侯爵であったり、あるいは男爵であったりする。
また、「奥州仙台陸奥の守、紺屋高尾がなぜ惚れなんだ」という有名なセリフがあるが、これも実話から脚色されたというから、洋の東西を問わず高級娼婦の地位は、田舎の百姓娘で終わるよりも数段上の、いわば輝ける地位であったに違いない。 娼婦という呼び方をするのは余りにも礼を失していて、その点、芸者という呼称は、もし心にしかるべき尊敬の念を持っている限り案外適切な言葉かもしれない。
芸者は、落籍され囲われた後もまだ芸者として続けて客席へ出るのが通例らしい。
私が今の会社を一緒に始めた山本象之助氏の家は大阪の住吉大社のすぐ裏手にあった。 隣家は梅田さんという中年の女性とその母の二人住まいだった。 聞けばそのすらりとした格好のよい女性は当時、ということは昭和二十七年ごろのことだが、南地随一の芸者で、そして近鉄の佐伯社長の二号さんとして有名であった。
普段は家に居たようだが、夕方になると三味線を抱えて外出する日があった。 山本氏が、「梅田さん、今日はどちらへ」と聞くと、「ハイ今晩は近鉄の宴会でお仕事です」と、答えていたのを憶えている。
この人などは、落籍後も芸者をしていた典型的な例と言えよう。 そしてこのような場合、囲うとか、囲われるとかいう言葉は不適切に過ぎるだろう。
私のロータリークラブの友人に、日本の洋画の元祖黒田清輝が描いた名画を数億円かけて、クリステイの入札で落札した人がいる。 仮にこの人をK氏と呼んでおこう。 K氏は南で芸者をしている美人の二号さんを持っている。 もっとも、二号さんと呼んでいいのかどうかしらぬが、彼女は相当賢く、しかも堂々としていらっしゃるらしい。時折、ロータリーの旦那方諸公ともゴルフに行かれるそうだ。 私は高級料亭にも、またゴルフにも縁がないのでまだお目にかかったことがないが、噂の様子からすると、どうやら、なまじのロータリアンなどよりは見識があり、しっかりしているらしい。 だからこそ、自ら恃む処の強いK氏が彼女を友人諸氏にご披露しているのだろう。
こうした旦那と女性の間柄というのは、必ずしも芸者という職業の女性にのみ限定されず、例えばクラブのホステスとその客の間でも同じと考えられる。コパカパーナのホステスをしていた根本という女性が故スカルノ大統領の三号夫人になり、そしていまではパリ社交界のヒロインなっていることは、テレビのドキュメンタリー番組で日本中が周知の事実である。 またビュッフェの絵の収集で有名な駿河銀行の頭取が銀座のクラブのホステスをしていた女性と、華やかな結婚式を挙げた話は週刊紙上格好の話題になった。
このように、世にときめく紳士方と特に親しくなった女性たちは、大抵の場合、美人であったからと云うようりは、むしろたぐい希な才女であったことに依るようである。 前の例で言えば、岡野氏の新夫人は四ヶ国語が堪能だそうだし、デヴィ夫人にしてもパリの社交界で長期間地位を保つためには相応の基礎教養が必要であることは想像に難くない。
昭和五十年ごろ、台湾で、日本でいえば初代貿易庁長官のような地位にあった張という人が北斗温泉の若い女性と結婚し、楽しそうに二人で中山北路を散歩して有名になったことがある。
張氏は、私の台湾のパートナーであった梅玉麟氏と共同で戦後の台湾の貿易システムや外国為替制度を作った人である。 私は、なぜ張氏のような名士が北斗温泉のホステスと結婚したのかと、梅氏に聞いてみた。
梅氏の答えは明快であった、
「いくら貧乏に生まれたとはいえ、立派な女性はいくらでもいる。張氏ほどの人が惚れるからには、惚れるだけの根拠があっただろう。 世間の蔑視にも耐えて、立派な女性と結婚するという行為は尊敬すべきであり、そしてそれこそ、西欧社会で言う浪漫ではないか。 台湾だけでなく、日本にもそのような例は幾らでもある。 桂侯爵の幾松を見よ、吉田首相のこりんちゃんを見よ」
と、梅氏は言った。 さすがに台湾財界に於けるジャパンロビーの第一人者だけあって、日本のこともよく知っていた。
政財界人で似たような例は幾らでもある。 もう一人だけ挙げてみよう。これも財界の消息通、佐藤正忠氏から聞いた話である。
東大在学中に共産党に入党し、転向して国策パルプを興し、財界に乞われて産経新聞の社長となった水野成夫氏に芸者上がりの二号さんが居た。 もうだいぶ老女である。 水野氏が出張の度に、彼女は東京駅のホーム迄やってきて、汽車の窓から手製の弁当を差入れていた。 財界の荒法師、水野氏は車中でこの弁当を頬張るのが習慣であって、それは財界でも有名だったそうである。 この二号さんにかかっては、水野氏も子供同然であったと謂う。話はそれるが、水野崇平という人がいた。 後にアラビヤ石油の社長になった人である。 水野成夫氏の子であったが、もともとアラビヤ石油の創業者、満州太郎こと山下太郎氏の実子である。産経新聞の鹿内信隆社長邸の晩餐会で、私はこの人と同席したことがある。 なかなかの理論家で、あとで聞いたところに依れば日本のラスキーという異名があったそうだ。 この人と面識を持った後、私は水野成夫という人は偉大なる怪物だと思った。 山下太郎氏の内緒の子をもらい受けたり、芸者をしていた二号さんに頭が上がらなかったり、やはり相当の大物だったのだろう。
またしても話がそれてしまった。 叔母、《しほ》の方へ戻ろう。叔母がどのような葬式をだしてもらったのか知らぬが、その後のことは解っている。ある日、叔母の兄弟たち、つまり私の母の男兄弟たちは、荷車を連ねて叔母の家財道具や衣装類を姫路から持ち帰った。さすが長らく都会で、物質的には田舎の農家などと比べものにならぬほど豊かな暮しをしていただけあって、その遺品は華やかで、そして多くにわたっていた。
いぶせき百姓家の六畳3 間にうず高く、そして乱雑に積み上げられた衣装・身の回り小物類はまさに百花繚乱、一生を農家で過ごす兄弟姉妹たちにとっては、ただただ目を見はるばかりであった。その驚きも束の間、形見わけの取り合いが始まった。
泣くなくも、奪い合いする形見わけ
という有名な川柳があるが、その通りの光景を十才の私は見た。その鮮烈な記憶は今も尚残っている。 さすがに男兄弟たちは、その分取り合戦への参加を躊躇したが、女たちは目の色を変えて華やかな衣類に殺到した。 彼女たちにとっては二度とないチャンスであった。 都会に住んだ一流芸者の衣装が田舎の百姓女の衣装として適切であるかどうかなど、考える暇はない。 今は只、なるべく美しそうな、そしてなるべく高価そうな着物を、如何に多く自分が取り込むかが唯一の目標であった。
女きょうだいの中で一番年下であった私の母は、そうした争いの場では勝ち目が少なかった。 それを知っていた母の母、即ち私の外祖母は、前もって母に耳打ちして争いに参加しなくてもいいと言った。 祖母は母のために目ぼしい物を、さきに内緒で取って置いてくれたのである。内緒の品は二つあった。 祖母の計算では、その価値は他の多くの衣装類を分け取りするよりも、より値打があるらしかった。 一つはダイヤモンドの帯締めであり、もう一つは泥大島の紬一疋であった。 一疋とは二反のことである。
米粒ほどのダイヤモンドではあったが、その帯締めは、母が一生の内に手にした物の中で紛れもなく最も高価で、そして最も身分に不釣合な品であったろう。母はよそ行きには必ずこの帯締めをして行った。 自慢の品であったが、田舎の百姓女の間では、ダイヤモンドなどは余りにもかけ離れた品であったから、自慢するほどのデモンストレイション効果はなかったようである。この帯締めは、後年私の商業学校の合格発表を見るため姫路へ同行した日に、何処かで落としてしまって遂に返ってこなかった。 母の悔しがりは終生続いていた。
もう一つの品、泥大島は、叔母が呉服屋の主人であった旦那に連れられて奄美大島へ行った折、買って貰った高価な反物だそうで、女物としては一番地味で小柄な亀甲模様の紬であった。 奄美大島では、泥のなかへ入れて焦げ茶色に発色させるから、これを「泥大島」と呼んで珍重するのだそうである。 著名な呉服屋の旦那がその寵妓と共にわざわざ産地まで行って、彼女のために買い求めた品であるから、相当高価な反物であることは想像に難くない。 それを彼女は着物に仕立てあげず、反物のまま亡くなるまで保管していたらしい。 そして、それを母が形見として貰ったという訳である。この大島の中の一反は、戦後すぐに母が私の丹前に縫い上げてくれた。 中茶の羽二重を裏地にし、薄い真綿を入れた丹前は、おとこ柄としては、少々派手にみえた。
長くお針の師匠をしていた祖母は、このような着物の衿は<七子(ななこ)の黒衿>でなければならないと言って、自分が嫁入り衣装に持ってきた着物についていた黒い衿をはずして、この丹前につけてくれた。
<七子>というのは塩瀬か絹ポプリンをもう少し分厚く、そして堅くしたような布であった。
物資が欠乏した頃のことであるから、私はこの丹前を冬の普段着として愛用した。それに黒い錦紗の帯をすると、軽く、そしてぞろりとした感触の<着流しの遊冶郎(ゆうやろう)>らしい風体(ふうてい)になり、間違いなく呉服やの若旦那という感じであった。当時、母は再び呉服やを始め、そして私はその手伝いをしていた。
その頃、田舎で素人の村芝居がはやった。 私どもの地区も青年団が芝居をした。雇われて姫路の町からやってきた芝居の着付け師がいた。 彼は不思議そうにまじまじと私の風体を眺めて言った、
「紛れもなく時代劇の二枚目侍の着物だ。その柄も、色あいも、そして全てが芝居の中そっくりだ。 不思議なことだ。ところで、一体あなたは誰なのか」。
そしてその時、私は初めて男の<着物の美>を認識した。 この美の基準は、わたし私の心の中で今もって変わらない。
この丹前は大阪へ出てきてからも愛用していたが、今はもう破れて無くなってしまった。 本当に惜しい着物であった。 あれだけの物はめったに無いだろう。
形見分けが終わった日の夕方、座敷の静寂(しじま)に取り残されたのは二冊の黒いアルバムだった。
一冊は亡くなった叔母の身内や友達の写真集だったが、もう一冊の方は芸者として出席した酒席や園遊会の写真を集めたものであった。おそらく当時の姫路財界の旦那方であろう人々が並んで写っている。
このようなアルバムは、今となれば姫路の珍しい現代史資料となるのではないかと思えるが、母の里に退蔵されたまま今日に至っている。
念のためにつけ加えておくが、旦那であった土井氏は、いま姫路の二階町にある土井呉服店の本家筋に当たるということであるが、詳しいことは知らない。芸者であった叔母の一生と、百姓家へ嫁いだ他の姉妹のそれと、どちらが幸せであったかということは、この文をお読みの諸兄姉の主観によることとしたい。
ところで、この初版を読んだある人が《芸者の話に数頁も費やしたのは少し多すぎるのではないか》と言ってきた。 確かにそうである。 しかし書いた理由は、こういう話であれば多くの人が興味を持って読んでくれるであろうと思い、少し多めに読者サービスをしたまでである。
[後註]それともう一つ。 ボクは年来、日本の花柳界システムについて興味を抱いてきた。 芸者、見番(けんばん)、花代(はなだい)などの仕掛けについてである。 花代などは、線香で芸者のサービス時間を計るとかで線香代(せんこうだい)などとも謂ったらしい。 赤坂や難波新地で散財する旦那衆にとってはあたりまえの知識かも知れぬが、ボクのごとき庶民にとっては、まことに怪奇で、伝統的で、そしてすでに消えかかった社会システムであって、いまとなれば新知識として取り入れがたい。
ところが最近になって、そのシステムの源流らしきものを発見した。 中国近代小説の代表作「海上花伝」である。 清朝初期の、上海花柳界を舞台にした通俗小説であって、芸者の出自から客の身元、そして漂客の遊びぐあいまで、どうやらほぼ戦前日本の花街そっくりで、この小説から類推するに、わが国花柳界のしきたりやシステムは、むかし上海から輸入されたものと考えられる。 「海上花伝」の「海上」は上海のこと、そして「花伝」とはそのものずばり「花柳界伝」である。 もはや古典ともいえる名著ゆえ、日本各地の図書館に、中国文学叢書の一部として蔵されているはずだから、一読をお勧めする。
前に述べたように、母のすぐ上の姉は鶴居村の豪商川口屋へ嫁いだ伯母《ぜん》である。九十才を過ぎてなお健在らしい。 五人の子を儲けて後、つれあいに死別したが、いわゆる後家の頑張りで、一生を働きずめに働いて、亭主から預かったものは遂に何一つ手放さなかった。 それでいて、障子や襖の切り張りに維新前の帳票類を解いて使っているのを見たことがある。 例えば、「近藤様御廻米始末帳」と青蓮院お家流墨字で書かれた紙虫(しみ)だらけの奉書紙が、勝手裏の障子に貼ってあったのを記憶している。
この維新前後に栄えた川口屋なる商家が何処から来、そして何故栄えたか、ボクは知らない。
私は生来アカデミックな対象は別として、通俗的、または社会的な物事にあまり詮索好きでない。この性質は近隣に迷惑を懸けないという利点はあるものの、このような文を書き始めると色々困ることが多い。 例えば、私は過去の資料とか記録というものを殆ど持たぬ。 そのため、古い話を持ちだしても、それがいつ頃のことかという定かな証明がない。すべてあやふやな記憶に頼るだけであるから、人の名前も日時もすべていい加減なものである。加えて、私はいわゆる蔵書というものを殆ど持たぬ。 書籍を買っても、読めばすぐ誰かに差し上げてしまう癖がある。 手元に残っている本は、買うときに失敗して、他人に差し上げるのもどうかと思う本か、そうでなければ少々難解で、もらい手のないような本である。 従って、このような文を書いていて、さてちょっと何か考証ということになると途端に困る。 見たい本が手元にないということは、想像以上に不便なものである。 もう少しはっきりさせてみたいと思うような命題に出会っても、適当に端折らざるを得ないのは残念である。
もっとも、<手元に本がある>ということと、自宅に本があるということとは別問題らしい。生前、親しくさせて頂いた阪大の故菅田栄治先生がこういうことを言っていた、
「郷里が島根県なので、大山(だいせん)の麓に山荘を持ち、そこで悠々と執筆しようとし、夏休みなどに大量の書籍を携帯していそいそと出かけたことがある。 ところが書き始めてみると、足らぬ本が沢山ある。あれも足らぬこれも足らぬで、結局、蔵書総てを移転して置かぬ限り山荘での執筆は不可能と解った」。
なるほど、そのようなものかも知れない。
菅田先生は、阪大で日本最初の「電子工学科」を創った電子顕微鏡の大家であり、後年、昭和天皇に<電子顕微鏡のご進講を申し上げた>ときのおみやげの、<菊の紋入り饅頭>の裾分けを私も頂いたことがある。
川口屋の濫觴などは私にとって面白い研究対象であるが、だからと言ってわざわざ時間をかけて、汽車に乗って姫路の奥の、中国山脈のなかほど市川の上流にある叔母の家まで調べに行く程の気もなかった。
ところが最近ある人が、それは河川交通時代の名残である可能性が強いと示唆してくれた。幕末から明治にかけて、日本中で一時期河川交通が盛んであったことがあり、 その当時栄えた多くは、河川交通を握っていた問屋商人たちであったというのだ。
なるほどと思い、念のため柳田国男の「故郷七十年」という最近有名になった本を見た処それらしき記述があった。柳田に依れば明治二年から数年の間、市川と円山川が、生野の銀山付近だけを馬でつないで、瀬戸内から日本海へ抜ける一連の河川交通路になったことがあったというのである。
とすれば、これでわが川口屋の存在理由が読めてきた。 亡くなった祖母の昔語りと年代も一致する。 それにかっての川口屋の縁組先が、殆ど但馬・丹波であったのも諾ける。更に、市川・円山川の河川交通が廃れた頃に川口屋が没落したのも偶然の一致ではない。 いまごろは水もろくに流れていない市川も、祖母の話では明治十年頃には川を運び下る米俵の高瀬舟をまだ見かけたとのことである。 市川上流の産米は、明治初年までは小舟で、姫路や飾磨津へ運んでいたらしい。
想像をたくましくしてみよう。 いま仮に、市川上流の旧粟賀藩一万石の産米のうちの半分、つまり五千石の米を換金すべく他領へ移送するとしよう。 行き先はたぶん大阪堂島か江戸、さもなければ京都と考えてよい。 そして積荷港は藩領内の市川に面した福渡、川口屋付近であったと考えるのが妥当な処だろう。
五千石は米俵の数にして一万二千五百俵になる。 生野銀山の産銀と違ってこれは膨大な量である。 馬の背で、生野の分水嶺を超えて日本海へ向かう円山川へ中継するには多すぎる。 当然、福渡から飾磨津へ下る舟に載せたと考えるのが常識だろう。
だが、飾磨へ下った舟が、福渡までまた戻って来るためにはどのような操船方法をとっていたのだろうか。 市川はこの辺りでは急流である。 いくら小舟とはいえ、船頭が櫓や竹竿で川の瀬を押して七里の距離を遡るのはそう簡単に出来ることではない。 ひょっとするとボルガの舟歌のように、川伝いに舟曳人足が唄でも歌いながら引っ張り上げたのかも知れない。
米俵は低価格の重量品であるから流れに従って下流へ運ぶのが得策である、が、その代金で京・大阪から買う消費物資などは軽量品が多い。 それらは市川をひっぱり上げずに、日本海から円山川経由で、生野の山越えで持ちかえったということも充分考えられる。
河川交通 幕末・明治初年の河川交通は柳田先生のご指摘に依るまでもなく、全日本的規模で非常に盛んであったらしい。 いま私の話している兵庫県中部を流れる市川・朝来川などは、もしそれが繋げたら大阪から日本海へ直接貨物が運べ、下関を回らなくていいのだから、まさに日本のパナマ運河ともいえる壮大な計画で、じじつ江戸末期から明治初年にかけて何度も企画され、ときには工事にさえ着手している。 (後註:ボクのwebsite,「名字帯刀御免 福本藩川口屋太右衛門」を見てほしい。)
維新前後の内国河川交通は、いまのわれわれが想像する以上に普遍化していた。
例えば、私の知人、山中康夫氏の実家などはその恩恵に浴した一例である。 氏はいま大阪に住んでいるが、実家は島根県の浜原という町であった。浜原は江の川の河口から五十キロも遡った中国山脈中の内陸港である。 大正の中ごろ迄、山中氏の実家はそこで「大津屋」という屋号の回船問屋を営んでいたそうで、毎年正月には、揃いのお仕着せを着た百人あまりの船頭たちが初荷のお祝い酒を振舞われる習慣があったという。
五十キロもの内陸にある河川港の一問屋の配下に百人の船頭が居たということは、当時の江の川の河川交通が如何に栄えていたかを示すに足る充分な証拠である。
この大津屋という屋号は、氏の先祖がどうやら滋賀県大津市からの移住であるためつけられたらしい。京都の港であった大津から湖北へ出、敦賀を経由して遥か遠く中国まで行った遣随使の道の中間点に江の川があったことからすれば、浜原の回船問屋が大津の出身であるというのは驚くに足らぬことかも知れない。
ついでにもう一つ河川交通に関係のある話を考えてみよう。私の生まれた福崎町八反田に勅使寺という廃寺跡があって、中世さる帝の妃が神積寺へ来たときこの寺に立ち寄られたらしい、ということは既に述べた。 帝とは後堀川天皇のことであるから、源実朝が暗殺された頃のことと考えられる。帝の妃、安喜門院(またはその代理)は勅使寺のすぐ側で下船したというから、市川を舟で来たのだろう。 とすれば、日本海と瀬戸内と、どちらから来たのだろうか。 もし北から来たとすれば、大津、敦賀、そして日本海を経由して朝来川(あさこがわ)を舟で遡り、生野峠を馬で越えて、また市川上流を下るということになる。 朝来川が舟で遡れたかどうか解らぬが、とにかく円山川という運河は当時まだ無かっただろう。 このルートはあり得そうな気がする。
しかし、もし安喜門院が北から来たのであれば、何故目的地である神積寺より二キロも川下にあるわが生れ故郷八反田で下船したのであろう。 そこに勅使寺があったからと言ってしまえばそれまでだが、何もそんなに川下迄行かなくても舟を下りる適地は川上にあった筈である。
反対に飾磨津から舟を遡らせて来たとしてみよう。 それであれば少し手前の勅使寺の辺りで下船したとしても不思議ではない。 この経路であれば、先ず、都を舟で発ち、淀川を下って浪速津へ出る。そこから須磨、明石、印南と海岸伝いに飾磨津へ達するのは上古以来の、官道としての海上交通路である。
播磨風土記に
「昔、神前の村に荒ぶる神ありて、毎に行く人の舟を半ば留めき」
という記述があり、その神前が何処の事か解らぬという話を、最近「日本の神々」という本で読んだ。
私は、この神前は我々神崎郡の神崎ではないかと思った。
ところが播磨風土記の中の様子では、神前という所はどうやら明石と印南の中間にあるらしい。念のためつけ加えると、神前も神崎も同じく帰化人系の普遍的な地名であって、日本中に沢山あるらしい。 先日も琵琶湖の近所へ十一面観音を見に行ったが、その辺りも神崎郡であった。私の子供の頃のクラスメートに神先君という少年がいた。相撲取りの増位山の従兄弟であると言っていた。 はやくに亡くなったが、彼は確か加東郡社町から通学していた。 社町付近に神先という姓が幾らかあればひょっとすると風土記にいう「神前の村」は社付近である可能性もある。神先と神前は同義語である。
遺伝学上の血縁度ー従兄弟か兄弟か ここで再び母の兄弟の方に戻る。1ダースに余る母の兄弟姉妹の中で偶然母と同じく八反田へ嫁して来たのが叔母の まさ である。同じ所へ嫁してきたと云うだけでなく、その嫁ぎ先は私どもの本家であり、亭主は父の従兄である。 叔母は沢山の子、つまり私の従兄弟たちを儲けた。 お互いの父親同士は従兄弟、そして母親同士は姉妹という間柄である我々従兄弟の血縁関係は、普通の従兄弟というより大分兄弟に近い間柄になる。 では両者の血縁は何処で違っているのかと云うと、それは両家のそれぞれの祖母が違うというだけである。 なぜなら、祖父同士はまた兄弟であったからである。 ややこしい話のようだが、結論から云えば、明治の始めに両家の祖母二人が、それぞれ別の所から嫁してきたというだけの違いである。本家の従兄弟たちと、私宅の兄弟との間柄は、いわば四分の三兄弟である。 そうすると遺伝学上どのようにお互いが似て来るのだろうかという疑問が湧く。
この疑問が解けそうなヒントが昆虫学のなかにある。 以下は大阪市自然史博物館の先生のお説である。蜂の仲間は、受精卵はすべて雌になり、不受精卵はすべて雄になる。雌は父親および母親から受け継いだ二組の遺伝子セットを持つが、雄は一組の遺伝子セットしか持っていない。 従って雄はすべて同一の遺伝子セットを次世代に伝えることになる。 この事により、蜂の血縁関係には独特の片寄りが生ずる。 親子間の血縁度は蜂の場合も人間の場合も二分の一である。 つまり子供の遺伝子の半分は確実に親から伝わったものである。兄弟の場合は少しややこしくなる。 人間にとって、自分の兄弟は全く自分と同じ遺伝子セットを持っている場合もあれば、全く違う遺伝子セットを持っている場合もある。 父親から貰った特定の遺伝子が、祖父からのものの事もあれば、祖母からのものの事もあるからである。 平均すれば、兄弟の血縁度は二分の一である。 蜂の場合は、父親から貰った遺伝子はすべて同一である。 従って自分の妹の遺伝子セットの半分は自分と共通している。 母親から貰った遺伝子は、同じ場合と違う場合とあり、確率としては母親からの遺伝子の二分の一を共有していると期待してよい。そうすると、自分と自分の妹の血縁度は四分の三となり、自分の子供との間より高いことになる。 つまり、働き蜂(不稔の雄)にとって、自分の子供を通じて遺伝子を伝えるよりも、自分の妹(女王)が多数の子孫を残してくれることに期待した方が得である。少々ややこし過ぎる話なので未だに釈然としないが、右のような蜂の遺伝パターンが理解できれば、本家の従兄弟たちと私どもの血縁度ないしは性質の類似性も数値化して客観視できるのではないかと考えている。 例えば、3/4x1/2=3/8 がその間の平均的相似度であるというように。 しかし念のために言えば、少なくとも外見上はお互いあまり似ていないようである。
本家へ嫁いで来た叔母は二年ほど前に九十才を過ぎて亡くなったが、生来歌が好きで、死ぬまで古い民謡や音頭を上手に歌っていたが、私の母が歌を歌っているのは遂に聞いたことがない。 そしてまた、本家の従兄弟たちは歌がうまいが、私たち兄弟の方はそれがからきし駄目である。
と、ここまで書いてきて、そして何気なく数字を書いた途端、ふと思い出したのだが、そしてそれは以前から折に触れ気にしている事だが、実は、私は数学がさっぱり駄目である。学校へ行っている頃に一応は、順列、組合せ、確率、二項定理まで習った筈だが、すっかり忘れてしまった。 社会生活に不必要であったから忘れたのであろうが、ひょっとすると必要であったかも知れない簡単な二次方程式ですら忘れてしまっている。 忘れたと言うより、始めから知らなかったのではないだろうか。
日常生活のための数学とは
四・五年ほど前にこんなことがあった。 当時の国際ロータリー266地区、つまり大阪府・和歌山県の全ロータリークラブから、日本にきている留学生に支給する寄付金を集める委員会の会合があった。 前年までは私がその責任者であったが、その年から武尾氏と交代した。武尾敬之助氏は住友電工の技術本部長か何かの役職を勤めた工学博士である。
竹尾氏は、その年の寄付の集まり具合いを「二次方程式に直すとこういうふうになる」と数式で説明された。
側に座っていた原田先生という老人がその数式を見て、「いや、それは違う。数式をこういうふうに直せば丁度当てはまる」と言った。 原田秀雄先生は昔、異例の若さで阪大の教授になった造船工学の大家である。
「なるほど」と言いながら武尾氏はその数式をすぐ訂正した。私はその時初めて「二次方程式」というものが実社会で必要な数学であると知った。
考えてみると、学校で教えるかぎり、その学問は社会に出て当然必要であるからこそ教える、ということは自明の理である。 にも拘らず我々は、こと数学に関する限り加減乗除だけが社会生活に必要であり、それ以上の数学は、学校で勉強すること、それ自体だけが目的であって、社会生活の道具や武器としては不必要であると思いこんできた。 だから例えば、「二次方程式」についての知識を社会でどのように使うかなど考えても見なかった。 確か、学校における数学の先生も「二次方程式」の実地応用法など我々に教えて呉れなかった筈である。
ひょっとすると数学の先生自身も、どのような場合に「二次方程式」を使うのか知らなかったのではなかろうか。
こう思った途端に、数学を日常茶飯事に使う武尾氏や原田先生が、私などの及び難い、いはば異質世界のエリートに見えて来、そして自分について激しい落後感に襲われたのである。 初歩的な数学さえ知らず、そして使えない自分が馬鹿に見えてきた。 私と同じように数学が出来ぬ友人諸氏は、こうした事態をどうお考えであろうか。私としては、せめて二次方程式くらいは実用に使えるよう勉強し直したい。 が、すでに年老いた。
さて、もう一人だけ母の兄弟をあげるとすれば末弟の福永又次になる。 外祖父の隠居した方の実家を継いだこの叔父はまだ健在である。
昔、あまりにも多くの子供が出来た時に、もうこれで終わりと言う親の願いが、お末とか留吉という名前になるが、それでもまた生まれたという場合に又次という名をつける習慣があったらしい。 川柳にある「末吉とお留の下にまた一人」、という典型的な例がこの又次という名をもらった叔父である。 本人はこの古くさい名前が一生不満であった。 いうなれば気の毒な話である。
叔父は気だてがよく、百姓仕事も熱心であった。 手先の動きが早いので野菜類の仕分けや整理に向いていた。 私の手仕事のスピードが少々早いのも、この叔父と同じ血を引いているからではないかと思う。早くして寡婦になった私の母を哀れと思ったのか、叔父は蔭になり日向になり数十年間、私たちを援助してくれたので、我々一家は彼に感謝しなければならない。
叔父は長らく子宝に恵まれず、とうとう諦めて嫁の末弟を養子にした。 これがいま跡継ぎになっている省吾君である。 省吾君を養子にするに当たって、忘れられぬことが一つある。 この話は彼にとって少々恥ずかしく感じることかも知れぬが、既に半世紀も前のことであるし、それに彼は物事に拘らぬよい性格だから公開してもたぶん苦情を云ってこないだろうと思う。
彼が叔父の家へ貰われてきたのは小学校六年生のときである。 叔父は彼を工業学校へ進学させるつもりでいた。 小学校の成績はクラスで二番だとの事であったから、工業学校の入学試験は充分合格する筈であった。 しかし、果して合格するかどうか心配して、工業学校の先生に手を回して、今で云う情実入学を企てた。
その先生というのは、私が小学生のころ田原小学校で先生をしていたが、習字科の中等学校教員検定試験に合格して先頃から工業学校の教諭をしているTという人であった。 T先生の近縁に当たる方が俳句の先生をしていて、その風雅な家が最寄りの溝口駅前にあった。
ある日、そこを借りて先生とその友人たち数名を接待することになった。 当時ぼつぼつ不足し始めていた配給の酒を何本か入手してその宴席へ運んだ。 料理は確か鶏のすき焼きであったと思う。
先生を始め数人の招待客は楽しそうに手をたたき、飲み、そして歌った。 私たちはその光景を庭の外から何時間も眺めていた。 たしか、宴会は夕日がさす頃まで続いたと思う。
ところが、いざ入学試験の合格発表をみると不合格になっていた。 これはおかしい、話が違うではないかという事になり、私が代表でT先生の家へ掛合に行くことになった。 私が十六才の頃であったと記憶している。
家まで押し掛け詰問する私を相手にしたのはT先生の奥さんであった。 先生は丁度その時、風をひいて寝て居られたらしい。 奥さんの言い分はこうであった、
「入学試験の当日T先生は病気で欠勤したが、気になるのでこの子は特に宜しく頼むと二重丸をつけたメモを試験委員の先生方にお渡ししておいたのだが、このような結果になって誠に申し訳ないと思っている」。
まだ子供であった私は腹がたって仕方がない。 さんざん先生の奥さんに文句を言い、「すぐ学校へ行って合格の方へ名前を書き換えてきてくれ」と本気で言った。 いまから考えてみると、いくら子供とは謂え随分無茶なことを言ったものだと汗顔の至りであるが、言われたほうの先生の奥さんからすれば、子供が怒鳴り込んで来たのだから面食らわれたことと思う。 恥ずかしい話である。
工業学校へは入れなかったが省吾君は立派に成長し、いまでは鉄工所を経営し、農業の方は副業になってしまった。 気だてもよく、叔父夫婦の面倒も充分みてくれるので、有難いことと思っている。 考えてみると、子供の頃に工業学校へ行ったかどうかなどは、彼の一生にとって大した問題では無かったようだ。
省吾君がようやく一人前になった頃、完全に諦めていた叔父夫婦に突然どうしたことか娘が生まれた。 文字通り玉のような女の子であった。 どうしてこのような美しい娘が生まれたのか不思議である。 神様は気まぐれである。
というのは、叔父もたいして男前ではないし、まして母親である叔父の嫁の方はどうひいき目にみても美人と反対の方であったからだ。 テレビスター叶和貴子に似たこの娘は成人して、教育大学の養護教員養成所に入学した。 学校が池田市にあったので、私は喜んで娘を三年間預かった。 なぜなら、これが私どもがお世話になった叔父への唯一の報恩の機会であると思ったからである。
もうこの娘も結婚して数人の子の親となっているが、盆暮れの贈り物をいま尚送って来る。
男とは
良いことずくめの叔父ながら、只一つ少し変わった処があった。 しかし、それは決して悪い方へ変わっているという訳ではない。 ただ、軍隊とか戦争とか、男たるものが一般的に話題にするような話に就いて、完全に興味が欠落しているだけの事である。
叔父の嫁は親戚内の出で、私の母が媒酌人と謂うことになっている。 嫁の父は前に述べた加西郡富田村の助役をした川島市次氏である。 第一次大戦で、駆逐艦「朝風」に乗って地中海まで遠征した海軍一等兵曹であり、太平洋戦争中は村役場の兵事係として軍国主義を鼓吹した。 長男、司(まもる)氏が海軍へ志願したのも、次男典男君が予科練へ行ったのも、たぶんにこの父君の影響である。 戦後まもなくの或る日、川島市次氏がしみじみ述懐してこういうことを言った、
「わが婿どのに就いて何一つ不満はない。しかし不思議に思うのは、日中戦争から太平洋戦争のあの長い十年間、婿どのは只の一度も戦争や軍隊のことを話題にしなかったことである。恐らく日本中のどんな人でも、そして例えそれがどんな否定的な意味であるにしろ、とにかく戦争中に一度や二度は戦争に関する話をしただろうに」。
確かに私も、片言隻句たりともこの叔父から戦争に関連する話を聞いたことが無い。だからと言って叔父に特別の意図や主義があっての事ではない。 とにかく、戦争とか軍隊とかに就いては一切気がないのである。
反対に、映画や芝居には目がなかった。 私はこの叔父に連れられて山田五十鈴の「湯島の白梅」を見に行った。 長谷川一夫の実演も見た。そして、宝塚の小夜福子が東郷健という年下のプロデューサーと結婚したということも知らされた。 いわば女性的な、いま風に言えば<フェミニン>な性格であったのだろう。
二十年程前、日生劇場で劇団「雲」による山崎正和の「野望と夏草」の初演を見たことがある。芥川扮する処の後白川法王が清盛に向かって「所詮、刀を執って野に争うのが男の使命、じっと耐えて子供を育て子孫を残すのが女の宿命」というような科白を言っていた。
考えてみると戦争とか、軍隊とか或はまた政治とか謂うものは、多かれ少なかれ勇ましいことの好きな「男」の、悲しい性(さが)の所産ではなかろうか。 そしてそれを、男のロマンというらしい。 わが叔父にはこの「男のロマン」がほぼ完全に、そして見事なくらい欠如していたのである。とは謂うものの、仕事は人一倍し、義務感もあるし、遂には子供も儲けている。 男として申し分がある訳ではない。
私の家から教育大学へ通学していた叔父の娘が卒業した折、三年間預かったお礼として叔父は私に何か呉れると言う。特に望んで「越後屋の図」の掛軸と、金胡粉の乾山風角鉢を貰った。

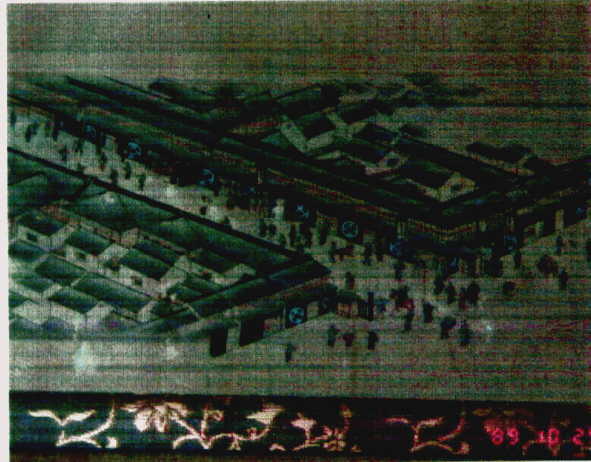
この絵には<山素絢>という落款があり、江戸時代のものらしく大和表装の軸である。 昔から叔父の家、つまり母の実家に伝わっていたものである。どのくらいの値打があるものかは知らない。美術年鑑で調べたが<素絢>の名は無い。 素川という名であれば、幕府の御用絵師の中に三人も居る。 尾形光琳の絵の先生は京狩野の山本素軒で、発音では<山素絢>に似ている。もし<山素絢>の山の字が、山本という姓の省略であれば、中国風の三字なまえが流行した徳川中期の絵である証拠になるかもしれない。 そして、素川も素軒も狩野派の絵師であるから、わが素絢も狩野派と考えられる。
絵は、三越の前身である越後屋とその前の大通りを斜め上から見おろした土佐派ないしは狩野派の構図で、大和絵風の霞をたなびかせて遥か遠くに富士山が見える。 軒先には屋号を染めぬいた暖簾が大きくはためき、馬に乗った侍や荷車曳きの人夫たちが大通りに沢山描かれている紙本淡彩画である。
いつ頃、どうしてこの掛軸を母の里が手に入れたのか誰も知らないが、私は少年の頃からこの絵が欲しかった。そして、いま貰って本望である。 さらに望むらくは画家<山素絢>の身元を知りたい。 どなたか、教えてくれる人はいないだろうか。
(後註:<山素絢>は解った。応挙十哲の一人、山口素絢である。 素絢の代表的な美人画は、ミシガン大学美術館にあり、但馬の応挙寺にも「猿」を画いた欄間絵がいたものがある。)
一般的に言って、田舎では、ある人がある特定の書画を持っている場合、似たような書画を近所の人も持っている可能性が大きい。古き良き時代、書家や画家は懐に金を持たず、筆一管で田舎を放浪し、その土地の素封家や数奇者の家に長い間無銭逗留する習慣があった。そして、その謝礼として書画を書くのが普通であった。 そうした書画家は、大抵の場合街道に沿った金持ちの家を順々に泊まり歩くことになるので、結果としてその街道筋の家々に似たような書画が残っているのは当然のことである。 例えば、箕面、池田、伊丹など旧西国街道筋に頼山陽の書画が多いようなものである。
しからば、わが郷里、神崎郡にはどの様な作家の書画が多いか。 まず、圧倒的に多いのは檪山(れきざん)という落款のある扁額(へんがく)であろう。 明治時代に神崎郡長であった淡路の人、檪山こと倉本雄三は能書家であった。 乞われるままに数多くの揮毫をした。 縦字の書は後日乱雑に扱われる可能性があるので、好んで扁額用の横書きの書を書いた。余りにも多く農家の鴨居に掲げられたので、世人称して「蜘蛛(くも)の巣在るところ檪山あり」と言った。
次に、霞湖という落款の南画風の彩色山水画が多い。 どこの人か知らぬが、旧田原村井の口の表具やに長逗留して相当沢山の絵を残した。 文展か帝展に二度程入選したプロの日本画家だったらしい。
安藤瓊巌(けいがん)という人の書も多い。 妙心寺派の管長をした高僧で、どのような縁故があったか知らぬが大正の頃神崎郡へ数回来たそうである。 最初は、その書を頂くのが大分難しくて値打もあったらしいが、二回目の来訪ではだいぶ沢山書き残したので有難みが減ってしまったそうである。 何れにしてもこの僧侶の掛軸は神崎郡一円に多い。 たいへんな能書である。
私の生家にもこの僧の三面一組の字襖があった。 落款の署名が余りにも流麗な草書なので、少年の頃の私はこの名前が読めず、そのため誰の書やら解らなかった。ある冬の日、松岡鹿松という変わり者で有名な表具師がこの襖の張り替えにやってきた。
この人は文盲であると世間では言っていた。その文盲の表具師が、数分間じっと襖の落款をにらんでから、やおら私に向かって言った、
「落款の最初の字は前とよめる。 そして次の字は妙心である。そのあとの字は解らない。何れにしろ京の妙心寺に関係がある人の字に違いない」。
そこで私は落款の最後に捺してある香炉の形をした印章の文字と草書の署名を比べて、後の三文字は「瓊巌書」であることを確認した。 もともとこの三文字は読み易かったのだが、始めの「前妙心」の字があまりにも勢いよく、そして流れるが如き立派な崩し字だったので読めなかったのである。 要するにこの書を書いた人は「前(さき)の妙心寺住職安藤瓊巌」老師であった訳だ。
しかしここに不思議なことが一つある。 それは、文盲であると言われた松岡鹿松氏がなぜ「前の妙心」と読めたかということである。 私にとってこの謎は未だに解けているとは言い難い。 彼は、本当は字が読めたのだ、といってしまえばそれ迄だが、私の知る限りでは、彼は確かに文盲であった。 いや、文盲に近かったと言うべきかも知れない。
文盲が襖字を書く不思議
この疑問を解くに値する鍵が二つばかりある。一つは、文盲の鹿松氏が不思議なことに沢山の襖の字を残しているという事実である。彼の次男は小学校で私と同級であったが、鹿松氏は我々の授業中に何度か息子の習字の筆を借りに来たことがある。 戦前、福崎辺りの百姓家では無地の襖紙を張る習慣が少なかったので、彼は襖の張り替えを依頼された折、その客先に張るべき絵や字がなければ、即席に自分で字らしきものを書き、それを襖に仕立て上げる事が多かった。 そのためには子供の習字用の筆が要るのであった。
何軒かの農家で私は、彼の書いた襖字を見たことがある。 字とは言えず、記号と言うべきかも知れない。いはば亀甲文字の如きもので、意味や内容などを知るに至るべくもない。
ある時私は何とか理解しようと思って、彼の字らしきものの前で思案の時間を費やした。 そして、そこで一つ解った。 何と、驚くべきことに彼の落款は「金竜山法念源空」と読めるではないか。浄土宗の開祖、法然聖人の名は確かに源空である。 法念聖人の寺の山号が金竜山であるというのも有りそうな話である。 彼はずっと以前、彼の書らしきものの原型となるべき書を何処かで見たようである。そしてそれを真似て、書らしきものを書き上げていたのである。 字を知らずとも字らしきものは書けるのではないか、というのがそれ以後の私の見解であった。
そして最近、その見解を裏ずけるような記事に遭遇した。 漢字ワープロの解説書の中に於てである。「ワープロとつきあう法」という本の中で科学技術大学の渡辺茂学長は次のようなことを述べている。ワープロ内部における漢字認識の方法は、特定の漢字の持つ漠然とした形状の認識から始まる。 例えば、縦に長い字とか、横に平べったい字とか、または三角形に近い字とか、或は斜めに字画の多い字とかいったような特徴を電子視覚で認識し、そうした字の特徴を次々に加算し、分析していって遂に目的の文字を捜し当てると謂うのである。 このワープロの漢字認識方法は、もともと人間の無意識的な漢字認識手段からヒントを得たものであるらしい。そしてこの方法であれば、正しい字を知らずとも、ほぼその字に近い字は認識出来る。一旦認識できれば、それに似かよった形状の字らしきものを書くのは易しい。これが第二の鍵である。
このような二つの鍵を勘案すれば、字を知らずして金竜山法念源空と読める文字らしきものを松岡鹿松氏が書けるというのは当然ではないか。更に言えば、数十年を表具師として過ごした鹿松氏であるから、字は知らずとも経験の蓄積で書画家の名前や落款についてある程度の専門知識を持っていたと考えても不思議ではない。私はこの人に可愛がられ、画仙紙の裏打ち法や掛軸の作り方などを教わったが、いまは殆ど忘れてしまった。
表具師松岡鹿松氏は今になって考えてみても不思議な人であり、そしてまた面白い人であった。 小柄ではあったが相撲をよくし、宮相撲、村相撲の類があれば必ず出向いて、軽量小兵よく大男の相撲取りを倒し観衆からやんやの拍手を得ていた。一度彼の家を訪ねたことがあるが、まさに<赤貧洗うが如き>という言葉を地で行く風情であった。 座敷らしき処には畳がなく、障子は破れ放題、家具は皆無で食器類もお茶碗数個のみという状態が一目で見え、本当にびっくりした。 如何に手元不如意とはいえ、これほどの貧乏所帯も珍しい。 仮にも表具師という本職があり、その名は近郊で通っているのだから、このあられもない貧乏住居は少々異様であった。 少年の私はその時、貧乏と言うことについて大きなショックを受けた。
後年、インドのネール首相の「無知と貧乏は追放されなければならない」という言葉に出会った時、先ず私の頭をよぎったのはこの折の情景であった。 もしそれがマルクスや毛沢東であれば、そこから革命への路線を突っ走ったかも知れない。
どうしてそのように貧乏だったか、という疑問はいまでも残っている。
ところが、この文を書いていてふとある考えが浮かんだ。それは、ひょっとすると彼のやむを得ない或る種の「生活形の獲得」ではなかったかと云うことである。
<生活形の獲得>というのは、例えば植物学で落葉樹が冬に葉を落とすという生活形式を進化の途中で獲得し、それに依って生物として生き長らえてきたというような場合に使う半ば専門用語である。 念のために言えば、落葉樹の中には、冬期ではなく乾期に葉を落とす熱帯の樹木も多く、植物進化論から言えばむしろ乾期落葉という生活形を獲得した樹木の方がより早く地球上に出現したのだそうである。
こうした考え方からいえば、わが鹿松氏もまた彼の貧乏所帯という生活形をある程度積極受諾した形式で獲得し、それに依って彼の数奇者(すきしゃ)としての人生を享受したのではないだろうか。 そしてそう考えてくると、彼が一生のうち何度か書画骨董で大損をしたという話や、三度の食事より相撲の方が好きであったと漏らしていたことなどと符合が一致してくる。
話をもとへ戻して、もしこの松岡鹿松氏による金竜山法然源空の襖をも書の中に加えるとすれば、これもまた神崎郡にたくさん存在している書と言えるだろう。
もう一つ例を挙げる。 画家、橋本関雪の父、海関の書のことである。最初私が海関の書を見たのは琴陵会の学友、増田利秋君の家であった。昭和十七年ごろのことと思う。
彼の家の奥座敷にあった四面の襖は墨痕鮮やかな海関の書であった。 草書とは言い難く、だからといって行書でもなかった。 妙な言いかたではあるがそれは草書と隷書の中間のような感じの書体であった。 墨痕鮮やかなその肉太の字は、丸みは一切なくただ峨々としてい、しかも不必要な線画のすべてを省いた、いわば簡体漢字とでも言うべき書体であった。 感覚的な表現をすれば「ナザレの荒野に冬が訪れた」というような感じの、簡潔で、そして荒々しく、さらに不屈の意志を加えた不思議な書であった。
詩文の内容は理解し難かったが、「不知楚州文世子一生窮達・・」云々の部分はいまも記憶している。 最近増田君にこの書の話をする機会があったが、彼によればもう時代は変わってしまって、そのような襖が彼の生家に存在しているかどうかすら疑問であるとの事であった。
次に海関の書にお目にかかったのは旧田原村辻川の醤油醸造家伊藤源次氏の家であった。
戦争たけなわの頃、配給の醤油を受取りに行った伊藤家の店の間は異様といえるほど沢山の書画で飾りたててあった。 ご親戚とかで、井上通泰・松岡映丘などの掛軸や色紙・短冊が多く、いはばミニ美術館という感じであった。その中にふと見ると、明かに一風変わった、そして見覚えのある海関の筆跡らしき軸があったので、「これは海関のようですね」と私は言った。 伊藤氏は途端に相好をくずして喜んだ。 「貴方は若いのに珍しく書画の知識がある。まあゆっくりと私の所蔵品を見てくれ」と言ったかと思うと、そのあと商売はそこのけにして映丘・通泰先生を始め秘蔵書画の講釈が二時間ばかり続いた。 合槌を打つのに少々苦労したが、帰りには配給切符の二倍の量の醤油を呉れたので嬉しかった。
増田利秋君の生家もまた醤油醸造家である。 そして増田・伊藤両醸造家とも北条・山崎街道に面しているのであるから、両家に同じく海関の書があったのは偶然とは言い難い。明石から三木へ出、そこから滝野を経て北条(加西)・辻川を通り、前の庄・山崎に至る道は中世以来播磨の国の主要な横貫街道であった。 そして、明石の人、橋本海関はこの街道筋の旧家・資産家を巡遊していたのではなかろうか。 往時、資産家といえば醸造家あたりが主であったから、増田君の家と伊藤源次氏宅に同じような海関の書があるのは充分諾ける処である。と、ここまで書いているうちに気になることが一つ出てきた。 それは伊藤源次氏所蔵の海関の軸はどのような文面であったか全然記憶がないと言うことである。 増田君の方に就いてはよく憶えているのに、もう一方のほうは皆目憶えていないと言ううのは少々不自然である。 ひょっとすると、それは書ではなく、絵であったかもしれぬ。 書家と画家はどちらも似たような視覚芸術家である。 書と絵と両方が書ける人は、中川一政や杉山寧の例を出すまでもなく非常に多い。 先日も作家の藤沢桓夫が新聞紙上で、画家の落款の文字はみな巧いと言っていたが、その通りである。
まして、関雪の父、海関のことであるから立派な絵も描けるだろう。しかし、もしその折の伊藤氏の軸が書でなくて絵であったとすれば、どうして私がそれを海関と即座に見抜けたのであろうか。 彼の落款の署名からかも知れない。 どうも私の記憶が・昧で解らぬことばかりである。 半世紀近い年月というものは、私の記憶を更に茫洋の彼方に追いやってしまうようである。
母の兄弟の話は取りあえずこの位にしておいて、父の兄弟の方へ移ろう。 と言っても、既に述べたように父には妹 ちか が一人いたきりである。 そのちかも子供三人を残して早くに亡くなってしまった。叔母、ちか の主人は中田といって長らく川崎航空機に勤めていた。 叔母がまだ生きていた頃、一家は神戸の下沢通り四丁目に住んでいた。 たぶん同級生の東郷猛君がいま小料理や「ぼんくら」を経営している辺りだと思う。
大工が作った飛行機
話によれば中田氏は川崎造船へはじめ大工として入ったそうである。 その頃、日本でも航空機を作ることになって、川崎造船所も若い技術者を外国へ派遣してその製造技術を導入した。大正初年のことであろう。
さて実際に造船所で航空機の試作ということになると、技術者だけでなく工員が要る。 現在のように軽金属材料がある訳ではないし、機体の主材料は木と布であった。 従って、多くの造船工員中より最初に選抜された航空機部門の工員は大工出身であった。 若い大工の中から職能優秀かつ品行方正ということで二人の青年が<名誉ある>初の航空機部門に配属された。 それがわが中田と、その生涯の親友、小原福松であった。
テレビの西部戦線映画で見る如く、昭和初年ごろまで航空機は木と布で出来ていた。 よくもあのような危なくて、そしてひ弱な機体で空が飛べたものと驚くほどである。川崎造船所でも、大工が、かんなと鋸とそして金槌で飛行機を作ったのである。 わが中田や小原青年にとって、航空機を作ることは名誉であり、自慢であり、そして楽しい仕事であった。 時代の最先端産業であり、しかもそれが大空を飛ぶ飛行機という、夢のようなものを自分たちの手で作るのであるから、彼らの喜びと自負心は、その話を聞く周囲の人たちまでも楽しくさせた。
その喜びを分つべく、中田氏は自分の作った航空機の精密な縮尺模型を造り、彼の妻の母に贈った。 小学生の頃、私の生家の床の間の天井には、この模型飛行機が吊り下げられていた。 単発双翼、二人乗りで、機体はすべて銀色に塗ってあった。下翼の両端に小さな棚のようなものが付いていたが、それは爆弾を積むところだという話であったから、たぶん軍用機であったろう。この模型はひょっとすると、わが国に於ける模型飛行機の第一号機だったかも知れない。
中田氏の夫人、つまり私の叔母は結核にかかり数年間病院暮らしのすえ亡くなった。三人の子供を抱えた中田氏はすぐ再婚した。 再婚相手は叔母の病気中ずっと家政婦として来ていた中年の女性であった。 しっかりもので、先妻の母、つまり私の祖母に対して義理をかかさなかった。
日中戦争から太平洋戦争と戦争は拡大し、川崎造船は航空機部門を分離して川崎航空機会社を創設した。 中田氏も転勤を重ね、各務原から神戸、明石と住居を移した。 社内に於ける地位も上がり、終戦直前、明石工場にいた頃は、部下も六百人ほど居ると同僚の小原氏が伝えてきたところをみると、中田氏の人生の最も輝けるときであったろう。氏が羽織袴に威儀を正し、晴れ着を着た家族全員と写した年頭写真が残っているが、見るからに自信にあふれ堂々とした姿であった。 大工から昇り詰めた彼の心境や如何に、と聞きたくなるような写真である。
しかし世の中はいいことばかりでない。 まず彼を困らせたのが長女と後妻の折れ合いの悪さであった。
長女は、父の転勤先である岐阜の女学校を終えた後、父と同じ会社へ勤めていたが、義母と折れ合いが悪く何回か家出を繰り返した。 その度に祖母が心当たりを探して連れ戻すというような事が続いた。 何回目かの家出の時、祖母は彼女を箕面に住む遠縁に預けた。
山下というその遠縁の人は、大阪で浪速紙業という紙問屋を経営し羽振りがよく、夫人は花街出身とかいうことであった。 彼女を預かった夫人はさすが苦労人らしく、祖母宛に懇切な手紙を何度も書いて、「立派なお祖母様のお孫様だけあって躾(しつけ)も行儀も行き届いているし、よく手伝いもしてくれる。どうぞご安心下さい」と言ってきた。
それでも心配でたまらず様子を見に行った祖母は、帰宅するなり 「箕面の桜が丘という所は大きな樹木がうっ蒼と繁って、家々はすべて上品な生け垣で囲まれ静かな高級住宅地であった」 と、私たちに報告した。
田舎に生まれ育った私にとって、それは想像もつかぬ美しい異国に思えた。 「桜が丘」という地名もまた、私の夢みる心を揺すぶった。
(後註:箕面桜ヶ丘は、日本初の洋風住宅博覧会が開催されたところ。広壮な江口治郎氏邸は、そのときの野外音楽堂の跡とか。)
躾について
ここで偶然使用した「躾(しつけ)」という言葉について、少々説明を加えておく。 私のつたない解説より、誰であったか忘れたが著名な先生のしつけに就いてのエッセイがあったのを思いだして、その大要を以下に述べる方がより明快だろう。
物の理をといて不合理なものを排除していく今日の教育とは、およそ違ったものであるが、実践を通じて生き方を一つの形として身につけてゆくことをシツケといった。「躾」と書いたがこれは中国にはない日本で作られた字である。つまり日本の庶民社会におけるシツケという感覚は、中国の文字をもつ社会にはなかったのであろう。シツケがよいというのは、その社会における共通感覚を身につけ、動作の上に<そつ>のないことである。 着物のシツケ糸のように、くずれない折り目をつけることがシツケである。このような知識伝承の方法は、文字が庶民社会へ入り込んできたあとも、村里では根ずよく残った。
以上のような「躾」についての解説は、なかなかよく出来ていて成る程とおもわせる。 文字がまだ成立していない未開社会でも、「躾」という共通規範によってある種の社会秩序が作れる。 これは集団社会にとって非常に便利がいい。私の経験から言えば、「躾」は日本のみならず欧州の各国、とりわけ英国にほぼ似たようなものがある。 武士のしつけが武士道であるとすれば、英国貴族のしつけは騎士道であろう。 そして、日本に於ける庶民のしつけに該当するものは、英国庶民の家庭教育によるマナーであろう。文字のない未開社会のみならず、言葉すら存在しない飼犬にまでしつけを援用する社会が西欧である。 先般テレビで、欧州のどこかの飼犬訓練学校のしつけ実習を放映していたが、これこそ「躾」教育の原点であり、そして終着駅ではないか。 それに比べると、大陸中国のことは知らぬが台湾、韓国、それに下層アメリカではしつけの概念が薄いような気がする。
心配していた祖母に対して、本人も「今度の所は静かなよい街で、女中さんまでハイヒールを履いているほどで、とても気に入っている」と言ったので私たちは一安心した。 しかしそれも束の間、彼女はここからもまた突然家出してしまった。その後、色々なことがあったが、結局のところ彼女は、彼女の父の部下と結婚し、子供を数人儲け、そして終戦になり、そして亭主が突然家出してしまって、終生苦労することとなるのである。
話は変わるが今から二十五年前、子供が学齢に達したので何処か良い小学校のある所へ転宅すべく家を探していた私に、ある不動産屋が「箕面市桜が丘」の住宅物件を持ち込んできた。瞬間に私の頭をよぎったのは <上品な生け垣の家々が並び、女中さんもハイヒールを履く箕面の桜が丘>という、少年のころの胸のふくらむ思いであった。不動産屋に連れられてその物件を見に行くまでもなく、そこへ移ろうと先に決心してしまった。
あとで解ったことだが、戦争中の山下氏の家は今の桜が丘二丁目で、古くからの高級住宅地であり、それに比べ、私が買った家は戦後に芋畑を切り開いた四丁目であって、だいぶ格が違っていた。 箕面へ転宅するとすぐ、私は遠縁にあたる山下氏の家を探したが、それは一時は解らずじまいであるかに見えた。
箕面市桜ヶ丘の今昔
しかし後日、箕面ロータリークラブへ入ったお蔭で、山下氏の家は既に無く、その在った場所は今の桜が丘二丁目であることが解った。 それは広大な江口邸の、すぐ東隣りであったことも解った。 そしてその付近に、今や私の友人が沢山できた。 友人とは、まず旧江口証券のオーナーで箕面随一の大旦那江口治郎氏、その友人である東洋紡の藤井豊氏、旧大井証券の大井治氏、ダイハツの会長を引退してロータリーのガバナーになった伊瀬芳吉氏などである。 特に江口氏には親交をいただき、氏から、「戦後すぐ山下と言う人が亡くなったあとその家は逼塞し、そこの娘さんが大阪の小料理やの板前と結婚し、そしてその小料理やへ何度か飲みに行ったことがある。」などの情報を得た。
箕面ロータリークラブ
江口氏、藤井氏、大井氏は箕面ロータリークラブの、それぞれ初代、二代、三代の会長であって隣同士の間柄である。 聞くところに依れば、その辺りは大正時代、日本で最初に高級住宅地として総合開発されたそうで、日本の住宅開発史上でも有名な所だそうである。 デベロッパーは「あめりか屋」といって今もその業界では老舗らしい。伊瀬芳吉氏の話では、毎年その方面の権威である早稲田大学建築科から「桜が丘住宅地の中の貴家の保存状態はどうなっているか、なにか変更はなかったか」というような内容のアンケートの手紙が舞い込むそうである。 数年前には、神戸大学の建築科の教授が国会図書館の青写真資料を持参して、氏の家の内部と照合させて欲しいと希望されたこともあるそうだ。この伊瀬氏が国際ロータリー第266地区のガバナーに就任されたとき、私は氏の後任として地区米山記念奨学会の仕事を託され、それ以後急速に親交を深め、今日に至っている。
江口氏の広い屋敷は、桜が丘住宅地の開発が完成した折開催された住宅博覧会における音楽堂の跡らしい。 私が今の箕面中央ロータリークラブへ移るまでの数年間、江口氏の命により氏を中心とした小さなグループ<る・さろん>を私が幹事役となってつくり、何度か江口邸へ参上したのも懐かしい思い出である。 ましてそこが少年の頃私が夢みた「箕面桜が丘」の親戚、山下政治氏の旧屋のすぐ隣家であることなど、不思議な因縁であるが、もし私の祖母や母が生きていたらどう思うであろうか。 ロータリー関係以外にも、貿専のフランス語の恩師、荘保三郎先生や、フェザー剃刀の藤本幸次郎老人など、以前から親しかった方々が偶然にもこの桜が丘二丁目の一角に大ぜい住んで居られるのを発見した。 荘保先生は、貿専の前身である府立高等貿易講習所の開校時に於ける専任講師兼学監であった。 先生の同級生である作家、藤沢桓夫氏のエッセイによれば荘保先生は語学の天才であったらしい。 逝去される前の数年間、私はよく先生の家を訪れた。 その間に、上品な奥様が亡くなられ、そして先生は英国婦人と再婚し、半分、学園前へ転居されたような感じであった。きけば新しい夫人も帝塚山大学の先生だったそうだが、遂に拝眉の機を逸してしまった。
フェザー剃刀の藤本氏は、私が会社を創業した折の共同経営者、山本氏の大阪高商時代の学友であった。 戦争中は桜が丘の在郷軍人会長であったが、それが郷友会と名を改えた現在ではどうなっているのであろうか。
従弟の死
川崎航空機の中田康二に嫁いだ叔母の二番目の子は長男順造であった。 私より一才年下で、似たような年格好であったから、小学生の頃は非常に親しかった。 毎年夏休みになると彼の一家は私の家へやってきた。 彼、順造君との間には、魚採りや水遊び、そして西瓜の食べ競べなど、あらゆる古き良き日の追憶がある。
戦火が大陸で拡大し始めた頃、彼も義理の母親と仲が悪くなったという事を聞いて、私は長い忠告の手紙を出したことがある。 彼は少しずつぐれ始めていたらしい。そして両親にとって困り者になっていたらしい。 父について行っていた川崎航空機の工場も欠勤し勝ちらしかった。ところがある日、手紙がきた。 彼は立ち直って真面目に働く決心をした。そしてその心を試すべく、敢えて望んで九州の炭坑へ坑夫となって行くことにしたと云うのである。当時、炭坑夫などというのは刑務所の囚人のような存在で、この世の地獄という意識が私の田舎にあったので、どうしてまたそのような所へ志願してゆくのか、不思議に思い、また哀れに思ったのを憶えている。
それから幾ばくも無いある日、突然にその順造君が亡くなったという知らせが入った。聞けば彼は、友人の坑夫たちと一緒に筑後川へ水泳に行って、水に溺れ死んだというのである。
思いかえせば、彼はどこかひ弱な影のうすい少年であった。 親に反抗していたなどとはちょっと考え難い、すなおで目だたぬ従弟というイメージが私に残っていた。 その順造君が死んだのである。 現地、九州の僧がつけたという彼の戒名は「夏水法順居士」であった。 まこと彼は夏の水に消えたのである。 哀れにも消え去ってしまったのである。 いまでも夏が来ると、そして藍色の大空のもとに川の水が白く光るのをみると思い出す。 夏水法順居士の戒名を。
それにしてもこのような、哀れにも記憶に残らせる戒名をつけた僧はどんな人であったろう。 心のきつい人か。 そうでなければこのように哀れな戒名をつける筈がない。いや、わけても心の優しい僧であったろうか。そうでなければ、かくも哀れな戒名をつける気にはならないだろう。十八才で死んだ従弟順造君は、この戒名と共に私の心の中に生き続けている。
順造君には妹が一人居た。 照子という。叔母が病気で寝ている間、照子は田舎に預けられて私たちと一緒に暮らした。そして彼女は村の幼稚園へも通った。しかし、半世紀、五十年以上も、彼女がどうしているか私たちは知らぬ。生きているのかどうかすら知らない。 彼女の姉に数十年前一度聞いたことがあるが、そのとき姉は、「あの子のことはもう聞かないで下さい。彼女も馬鹿ではないし、自分で何とかしているでしょう」というような返事だったので、それ以上は聞きそびれてしまった。 当時彼女には、何か特別の事情があったのだろう。私の歳も既に還暦を過ぎた。 もはや、過去にこだわりもなく、てらいもない。いちど暇をみて彼女を探してみたいと思っている。
中田康二氏は終戦と同時に川崎を退職し、女子師範学校前に買い求めていた自宅も売り払って、後妻との間にできた小さい子供たちを連れて、夫婦ともども、明石海岸にある市営母子寮の住み込み管理人になった。 手際がよいというか、いざぎよいと言うべきか、まことに見識家であったようだ。
昭和三十五年ごろ、祖母が亡くなったとき、中田氏に葬式の通知をだすべきかどうか、ちょっと思案した。 もう長く付き合いも途切れているし、それに先方には後妻とその子供たちもいるのだから、遠慮しようということになった。 しかし、同じ母子寮の一角に住んでいる長女は、何れにしろ故人の孫に当たるので黙っている訳にはいかぬだろう、とのことで長女にあて葬式の電報を打った。 長女は涙を流しながらすぐ駆けつけた。 中田氏も僅かに後れてやってきた。まことに律儀な人であった。
それから数年のち、私は思い立って或る日曜の一日、母子寮に彼ら親子を訪ねたことがあった。
中田氏は、年老いた母子寮の管理人らしい風体に変わってしまって、かって川崎航空機に勤めていたころの自信にみちた面影はなかった。長女の方は、亭主に去られ、幼い子供たちを抱えて苦労を重ねている様子がありありと見えた。 しかし気丈にも、
「あたしたちは貧乏でも幸せよ、ねえxxちゃん」
と、なかば傍らの子供に向かって言い聞かせるようにいった。 だが、私の目にはどうしても幸福とは見えなかった。 人が幸福であるかどうかどうかは、むしろ客観的な他人の目で判定すべきで、本人の主観に依るべきものではないと、そのとき思った。そしてその後、絶えて久しくこの人たちと会う機会もない。 果してまだ健在であろうか、そして幸せであろうか。
中田康二という人は、はいまや私たちにとって、地区の氏神八坂神社の玉垣にその名をとどめるのみとなってしまったようだ。
今年花落ち 顔色改る 明年花開くとき 復た誰か在る
巳に松柏の砕けて薪と為るを見 更に聞く桑田変じて海と成るを
古人洛城の東に復るもの無く 今人還って落花の風に対す
年年歳歳花相似たり 歳歳年年人同じからず
と謂うことか。
さて、次は私のことになる。